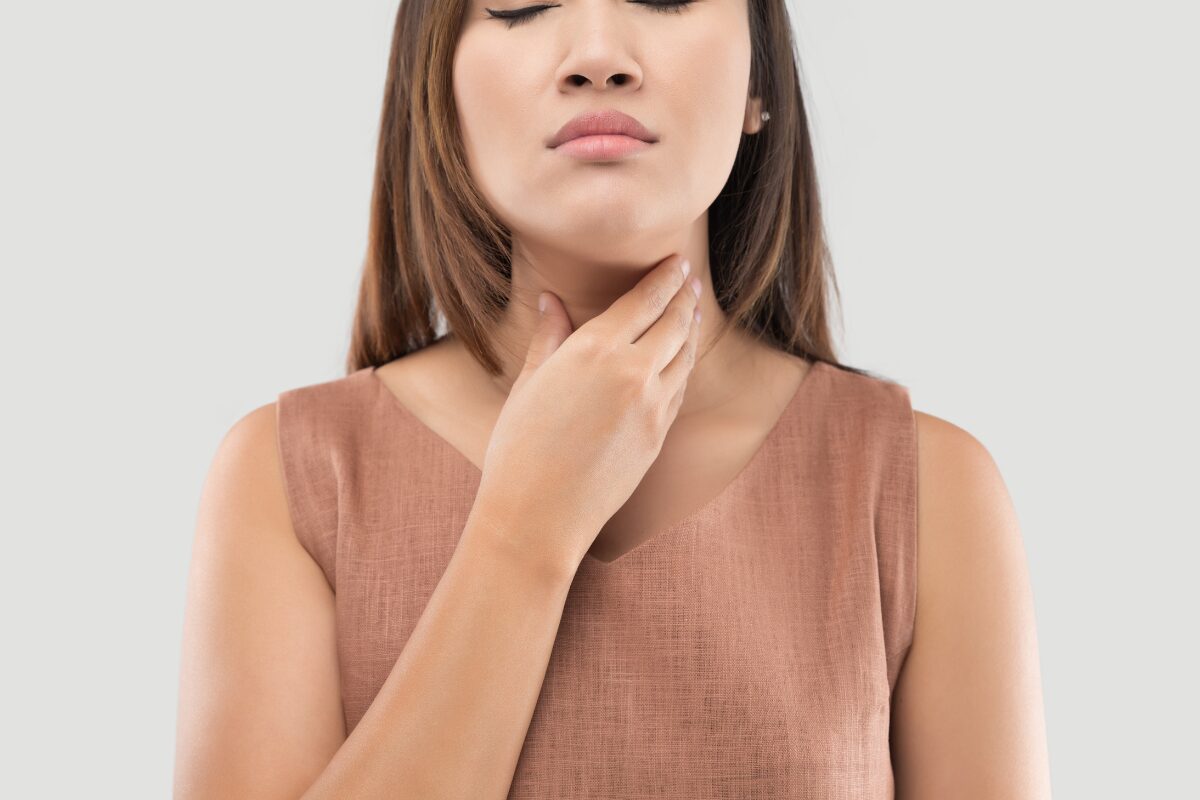
喉に違和感やつまり感を覚えるのに、病院の検査では「異常なし」と言われてしまう――そんな経験はありませんか?
このような症状は「咽喉頭異常感症(いんこうとういじょうかんしょう)」とも呼ばれ、ストレスや自律神経の乱れが関係しているとされるケースも少なくありません。
しかし、整体の現場では、こうした喉のつまり感に対して身体のゆがみや緊張だけでなく、心の抑圧や“本音を飲み込む”という心理的傾向も深く関係していると考えています。
本記事では、整体的な観点から見た喉のつまり感の原因と、意外と見落とされがちな心理的・感情的背景について掘り下げながら、改善へのヒントをご紹介していきます。
喉のつまり感とは?考えられる一般的な原因

喉の奥が詰まっているような感覚、何かが引っかかっているような違和感。
飲み込みにくさや圧迫感を伴うこれらの症状は、「喉のつまり感」や「咽喉頭異常感(いんこうとういじょうかん)」と呼ばれ、多くの方が一度は経験したことのある不調の一つです。
しかし、内科や耳鼻科で検査を受けても「特に異常は見つかりません」と言われることも多く、原因がはっきりしないまま悩み続けている方も少なくありません。
ここでは、医学的に知られている喉のつまり感の主な原因について見ていきましょう。
■ 咽喉頭異常感症とは?
病院で「特に病気はないけれど、喉に違和感がある」と診断される場合、多くは咽喉頭異常感症という名称で扱われます。
これは、器質的な異常(腫瘍や炎症など)は見つからないにもかかわらず、喉に不快感や異物感、圧迫感などを感じる症状を指します。
咽喉頭異常感症は、ストレスや緊張、精神的な影響、自律神経の乱れなどが関与していることが多く、「心因性の症状」として扱われることもあります。
■ ストレスによる自律神経の乱れ
喉は自律神経の影響を受けやすい部位です。過度のストレスや不安が続くと、自律神経のバランスが崩れ、喉や胸の筋肉が無意識に緊張してしまいます。その結果、「喉が締めつけられるような感覚」や「何かが詰まっている感じ」が起こるのです。
特に、**交感神経が優位な状態(緊張・興奮モード)**が続くと、筋肉のこわばりや呼吸の浅さも影響し、喉の違和感として現れやすくなります。
■ 胃酸の逆流(逆流性食道炎)
喉のつまり感の原因としてもう一つ挙げられるのが、胃酸の逆流です。胃酸が食道や喉に逆流すると、粘膜を刺激し、違和感や咳、声枯れなどを引き起こすことがあります。これを逆流性食道炎あるいは喉頭アシドーシスと呼びます。
ただし、逆流性食道炎の場合は胸焼けや胃もたれなど、ほかの消化器症状も伴うことが多いため、区別の手がかりとなります。
整体的に見る喉のつまり感の原因

「喉がつかえる」「何かが引っかかっている感じがする」といった症状があるにもかかわらず、病院では「異常なし」と診断されてしまう。
そうしたケースは、実際に整体の現場でも少なくありません。原因がはっきりしない不快な症状が続くと、不安が募り、より一層緊張が高まり、症状が慢性化してしまうこともあります。
整体の視点では、喉の違和感やつまり感も、全身のバランスの乱れや筋肉・関節の緊張、呼吸の浅さ、自律神経のアンバランスなどと深く関係していると考えます。以下に、喉のつまり感に関連する主な身体的要因を詳しく解説していきます。
■ 姿勢の乱れと首・胸郭の緊張
現代人に多い「猫背」や「ストレートネック」といった姿勢の乱れは、首や喉まわりの筋肉に慢性的な緊張を与えます。
とくに首の前側にある**胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)や斜角筋(しゃかくきん)**といった筋肉は、日常的に過剰に使われやすく、こわばりやすい部分です。
このような筋肉が緊張すると、喉に圧迫感を与えたり、喉周辺の血流やリンパの流れが滞り、違和感やつまり感として現れます。
また、胸郭(肋骨まわり)の動きが固くなると、喉を通じて行われる呼吸や発声にも支障が出てくるのです。
■ 呼吸の浅さと横隔膜のこわばり
喉の症状と深く関わるのが「呼吸の質」です。
日々のストレスや不良姿勢の影響で呼吸が浅くなっている方は非常に多く、これにより首や喉まわりの筋肉に余計な力が入りやすくなります。
呼吸の中心となる**横隔膜(おうかくまく)**が緊張すると、胸郭や腹部の動きが小さくなり、呼吸が「喉や胸の上部」だけで行われるようになります。
このような呼吸パターンは、喉の動きを不自然にし、常に緊張を強いられるため、つまり感が慢性化しやすくなります。
整体では、横隔膜や肋骨まわりの動きを調整することで、自然な深い呼吸を取り戻し、喉への負担を減らすアプローチを行います。
■ 背骨・顎関節のゆがみとの関係
意外に見落とされがちなのが、背骨や顎関節のゆがみです。
特に首の骨(頸椎)の並びが乱れていたり、顎の動きに左右差がある場合、喉まわりに不要なストレスがかかることがあります。
頸椎のゆがみは、自律神経にも影響を与え、喉の緊張を高める原因になります。
また、顎関節のズレやかみ合わせの問題があると、無意識に舌の位置や喉の奥の筋肉に力が入り、違和感が生じやすくなります。
整体では、頸椎や顎まわりの微細な調整を通して、喉が自然にリラックスできる状態を整えていきます。
■ 自律神経の乱れも無視できない
喉のつまり感は、自律神経のバランスの乱れとも密接に関係しています。
交感神経が過剰に優位になると、体は常に緊張状態となり、喉まわりの筋肉もこわばってしまいます。
「人前で緊張して喉が締めつけられるような感じになる」「ストレスを感じると喉に違和感が出る」というのは、まさに自律神経の乱れによる典型的な反応です。整体では背骨や頭蓋骨まわりを調整し、自律神経が安定しやすい状態を作り出します。
本音を抑えることが引き起こすのどのつまり

■ 本音を言えないことが招く「のどのつまり感」
私たちは日常生活で、時に本当の気持ちを押し殺してしまうことがあります。
「言いたいことが言えない」「自分の意見を飲み込む」そんな経験は、多くの方に共通するものです。
しかし、この「言えない心のしこり」は、単なる心の問題だけに留まらず、身体にも現れてきます。
特に、喉は「声を出して表現する場所」であるため、本音を抑え込むほどに緊張しやすく、「のどのつまり感」として感じられることが多いのです。
のどのつまりは、感情のエネルギーがうまく流れず、身体に停滞しているサインともいえます。
言葉にできない思いが喉に重くのしかかり、体はその違和感を不快な症状として表現しているのです。
■ のどのつまりが示す心の抑圧と感情の滞り
のどのつまり感は、単なる筋肉の緊張だけでは説明できない場合があります。
それは、心の深い部分で「自分の気持ちを押し込めている」ことの表れであり、感情の滞りそのものです。
怒りや悲しみ、不安といった負の感情を感じても、認めずに押し込め続けると、エネルギーが詰まってしまい、のど周辺に強い圧迫感や違和感をもたらします。
この状態が続くと、ますます感情を言葉にできなくなり、悪循環に陥ることもあります。
そのため、のどのつまりは「心のサイン」として受け止め、無理に抑え込むのではなく、少しずつ解放していくことが必要なのです。
■ スピリチュアル視点で見るのどのつまり:第五チャクラのエネルギー
スピリチュアルな観点から見ると、のどは「第五チャクラ(スロートチャクラ)」にあたります。
このチャクラは自己表現やコミュニケーションを司り、エネルギーの流れが滞ると「言いたいことが言えない」「伝わらない」などの問題が現れます。
のどのつまり感は、この第五チャクラがブロックされている状態を示すことが多く、心と身体、エネルギーの三位一体のバランスが乱れているサインとも言えます。
整体の施術は身体の調整だけでなく、このチャクラのエネルギーの流れを促し、のどのつまり感の根本的な改善に繋げていくことが可能です。
■ のどのつまりを緩和する心と体の整体アプローチ
のどのつまりは、身体的な緊張の解放と共に、心の抑圧を少しずつ解きほぐすことが鍵となります。
整体では、首や胸郭、背骨を整え、筋肉の緊張を緩めることで喉の動きをスムーズにしていきます。
さらに、呼吸を深く促すことで、体内のエネルギー循環を改善し、自然と感情の解放をサポートします。
同時に、「本音を少しずつ言葉に出す」「感情を書き出す」などのセルフケアを併用することで、心と身体のつながりを強化し、のどのつまり感を根本から軽減することが期待できます。
整体の施術と心のケアを組み合わせることで、のどのつまりは単なる症状ではなく、あなた自身の自己表現と癒しの第一歩となるのです。

