
「整体を受けたあと、体が軽くなるだけでなく、気持ちまでスッと晴れたような感覚になることはありませんか?」
多くの方が整体後に感じるこの「心地よさ」や「安心感」には、実は科学的な裏づけがあります。それが、私たちの体の中で自然に分泌される“内因性オピオイド”と呼ばれる物質です。
内因性オピオイドは、ストレスを和らげたり、痛みを軽減したりといった役割を持つ、いわば「体内の癒しホルモン」。整体によってこの物質の働きが活性化されることで、体と心が同時に整っていくのです。
今回は、この“自然な癒しのメカニズム”と、整体との深いつながりについて、わかりやすくご紹介していきます。
内因性オピオイドとは何か?
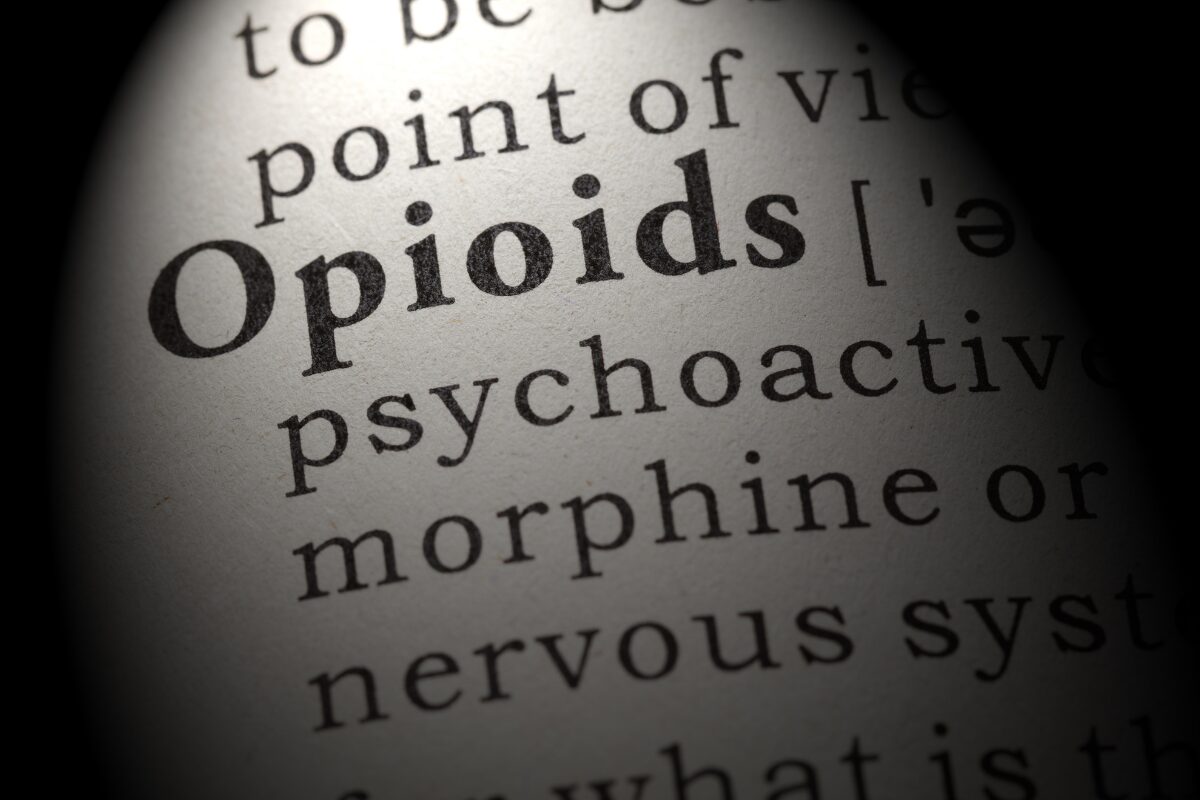
人間の体には、痛みやストレス、外部からの刺激に対して、自らを守り回復させるための内因性の鎮痛・安定システムが存在しています。その中心的な働きを担っているのが、「内因性オピオイド(endogenous opioids)」と総称される一群の神経ペプチドです。
内因性オピオイドとは?
内因性オピオイドは、脳や脊髄を含む中枢神経系、および末梢神経系において生成・分泌される神経伝達物質で、私たちが痛みやストレスを感じたときに、それを和らげるように自然に放出されます。
その作用は、モルヒネやフェンタニルなどの合成オピオイド薬と非常によく似ており、オピオイド受容体と呼ばれる特定の神経細胞膜上の受容体に結合することで、神経伝達を調整し、鎮痛、鎮静、幸福感の促進などの効果を発揮します。
このため、内因性オピオイドは「天然のモルヒネ」とも称され、医療分野や脳科学、心理学でも大きな注目を集めています。
主な種類と働き
1. エンドルフィン(Endorphins)
-
「エン(内なる)・ドルフィン(モルヒネ)」=endogenous morphine(体内モルヒネ)から命名。
-
激しい運動や感動、笑い、音楽、深いリラクゼーションなどによって分泌され、強い鎮痛効果と快感・高揚感をもたらす。
-
ランナーズハイや瞑想中の多幸感は、エンドルフィンの分泌によるとされる。
-
主にμ(ミュー)オピオイド受容体に作用。
2. エンケファリン(Enkephalins)
-
脳と脊髄に広く分布し、痛みの伝達を遮断する役割を担う。
-
即時的な鎮痛効果よりも、痛みの感受性の調整や抑制に寄与。
-
情動ストレスや軽度の刺激にも反応し、日常的に働いている。
3. ダイノルフィン(Dynorphins)
-
他の内因性オピオイドよりも強力な作用を持つ。
-
κ(カッパ)オピオイド受容体に作用し、痛みの制御、記憶、情動反応に関与。
-
一部の状況では、痛みを増幅させたり不快感をもたらす場合もあり、防衛的役割があると考えられている。
内因性オピオイドの生理的役割
● 鎮痛作用(Analgesic Effect)
オピオイド受容体に内因性オピオイドが結合することで、痛み信号の神経伝達をブロックし、脳が痛みを認識しにくくなります。これは身体のどこかに傷や炎症があっても、精神的にリラックスしていれば痛みをあまり感じないといった現象の背景にある仕組みです。
● ストレス緩和(Stress Modulation)
内因性オピオイドは、視床下部-下垂体-副腎軸(HPA軸)の活動を抑制し、コルチゾールなどのストレスホルモンの過剰分泌を抑える働きがあります。これにより、不安感や過緊張を緩和し、心を落ち着かせます。
● 多幸感・安心感の促進(Euphoria & Well-being)
エンドルフィンなどのオピオイドは、ドーパミン報酬系とも連動しており、幸福感や快感、満足感をもたらします。これにより、「癒された」「安心した」「気持ちがいい」といった主観的な感覚が生まれます。
整体と内因性オピオイドの関係

整体による施術が、単なる筋肉や骨格の調整だけでなく、心身の深いリラクゼーションや痛みの緩和をもたらすことは、多くの人が実感していることです。こうした効果の背景には、「内因性オピオイド」の分泌が促進されている可能性が、近年の生理学的研究によって示唆されています。
副交感神経が優位になる“安心モード”へ
整体施術中、リズミカルで穏やかな刺激が体に与えられると、自律神経系のうちの副交感神経(リラックスを司る神経系)が優位になります。副交感神経の活性化は、呼吸や心拍、血圧を落ち着かせ、体を「戦闘モード」から「回復モード」へと切り替えます。
この“安心モード”に入ったとき、脳内では内因性オピオイドが自然に分泌されやすくなると考えられています。これは、深い瞑想中や入浴、安らぎを感じる音楽を聴いているときと同様の生理反応です。
「手当て」や「触れる」ことの科学的効果
整体では、施術者の“手”が直接、クライアントの身体に触れます。この「触れる」という行為そのものが、脳に安心を伝える非常に重要な刺激になります。皮膚には圧力や温度を感知する受容体が多数あり、やさしく触れられることでオキシトシン(愛情ホルモン)やエンドルフィンといった神経化学物質の分泌が促されることが知られています。
このような身体接触による神経系の反応は、「痛みが和らぐ」「不安が減る」「気持ちが落ち着く」といった主観的な感覚に結びつき、内因性オピオイドの作用を強化する効果も期待されます。
やさしい刺激・ゆがみの解放・リズムがカギ
整体では、強い圧力や痛みを伴う刺激は避け、やさしく、かつ的確なアプローチが大切とされています。これは、身体が過度の緊張を感じずに副交感神経優位の状態を保ち、内因性オピオイドを最大限に活かすために理にかなった方法です。
-
やさしい刺激は皮膚や筋膜に適度な圧を与え、安心感を生み出します。
-
身体のゆがみの解放は神経系の過緊張を解き、自然な感覚入力を回復させます。
-
リズミカルな調整(呼吸や体の自然な動きに合わせた施術)は、脳波や自律神経の安定化につながります。
こうした要素が組み合わさることで、脳は「今、安心してよい」というメッセージを受け取り、内因性オピオイドを自然に放出しやすくなるのです。
「気持ちが軽くなった」「眠くなった」という声の意味
実際の施術後には、「気持ちが軽くなった」「深く息が吸えるようになった」「急に眠くなった」という声をよく耳にします。これらの反応は、身体が緊張から解放され、神経系が回復・再生モードに入ったサインであり、まさに内因性オピオイドの作用が発揮されている可能性を示しています。
また、痛みが和らぐだけでなく、感情的な安堵感や「なぜか気分が良くなった」といった変化も、こうした神経伝達物質と自律神経の変化が連動している証拠といえるでしょう。
内因性オピオイドが活性化されることで期待できる効果

内因性オピオイドは、体内で自然に作られる「痛み止め」かつ「心の安定剤」とも言える物質です。この物質が活性化することによって、私たちの心身にはさまざまな良い変化が現れます。整体などの施術によってこの内因性オピオイドが促されることで、単なる一時的なリラクゼーションを超えた深い治癒効果が期待されるのです。
1. 慢性的な痛みの緩和
エンドルフィンやエンケファリンといった内因性オピオイドは、脳や脊髄で痛みの信号をブロックする働きがあります。これは外部から投与されるモルヒネと同様のメカニズムであり、慢性痛に苦しむ人にとっては自然かつ副作用のない“鎮痛システム”です。
特に腰痛や肩こり、神経痛のような慢性症状に対して、整体によって副交感神経が活性化され、内因性オピオイドが分泌されることで、痛みの感受性が下がり、症状が和らぐことが期待できます。
2. ストレス耐性の向上
ストレスにさらされたとき、脳内では緊張や不安を引き起こす神経伝達物質が優位になりますが、エンドルフィンはそれらを中和し、精神的な緊張を緩和する効果があります。まさに“天然の抗ストレス剤”とも呼べる働きです。
整体施術後の「なんだか安心した」「ほっとした」という感覚の裏には、このオピオイド系の作用が関係していると考えられます。
3. 睡眠の質の向上
エンドルフィンの分泌は、自律神経のバランスを整え、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌をサポートするという効果もあります。そのため、内因性オピオイドの活性化は、入眠のスムーズさや睡眠の深さを改善する可能性があるのです。
整体の後に「眠くなる」「ぐっすり眠れた」という反応が多いのも、神経系の調整とオピオイド作用の相乗効果によるものです。
4. 気分の安定(うつ・不安の軽減)
内因性オピオイドは、気分の安定に深く関わる脳内物質の一つです。特にセロトニンやドーパミンとも相互作用し、うつ状態や不安感の軽減に寄与します。これは近年の神経科学の研究でも明らかになってきています。
整体によって身体の緊張が解け、同時に脳内でもこうした化学物質のバランスが整うことで、施術後の「気持ちが晴れた」「前向きになれた」といった感覚が生まれるのです。
5. 自然治癒力の向上 → 施術効果の持続にもつながる
内因性オピオイドは、単なる鎮痛効果やリラックス効果だけでなく、免疫機能の調整や炎症の抑制にも関与しています。つまり、オピオイドが活性化されると全身の自然治癒力そのものが高まるのです。
これにより、整体の施術によって整えられた身体の状態が、より長く、深く持続しやすくなります。症状の一時的な緩和ではなく、根本的な体質改善や回復力の底上げが目指せる点で、非常に重要なメカニズムといえるでしょう。

