
突然、胸がドキドキして息が苦しくなる。
このまま倒れてしまうのではないか――そんな強い不安に襲われた経験はありませんか?
病院で検査をしても「異常なし」と言われ、心療内科では「パニック障害」と診断されることもあります。
けれど実は、その発作の裏側に体のエネルギー(血糖)の乱れが潜んでいることが少なくありません。
パニック発作と低血糖発作はとても似ていて、動悸や手の震え、冷や汗、強い不安感など、症状もほとんど同じです。
心の問題としてだけではなく、体の内側のバランスを整えることが回復のカギになる場合もあるのです。
今回は、そんな「パニック障害と低血糖」の関係について、そして整体と栄養療法を組み合わせて心を安定へ導く方法をお伝えします。
パニック発作と低血糖発作の驚くほど似た症状
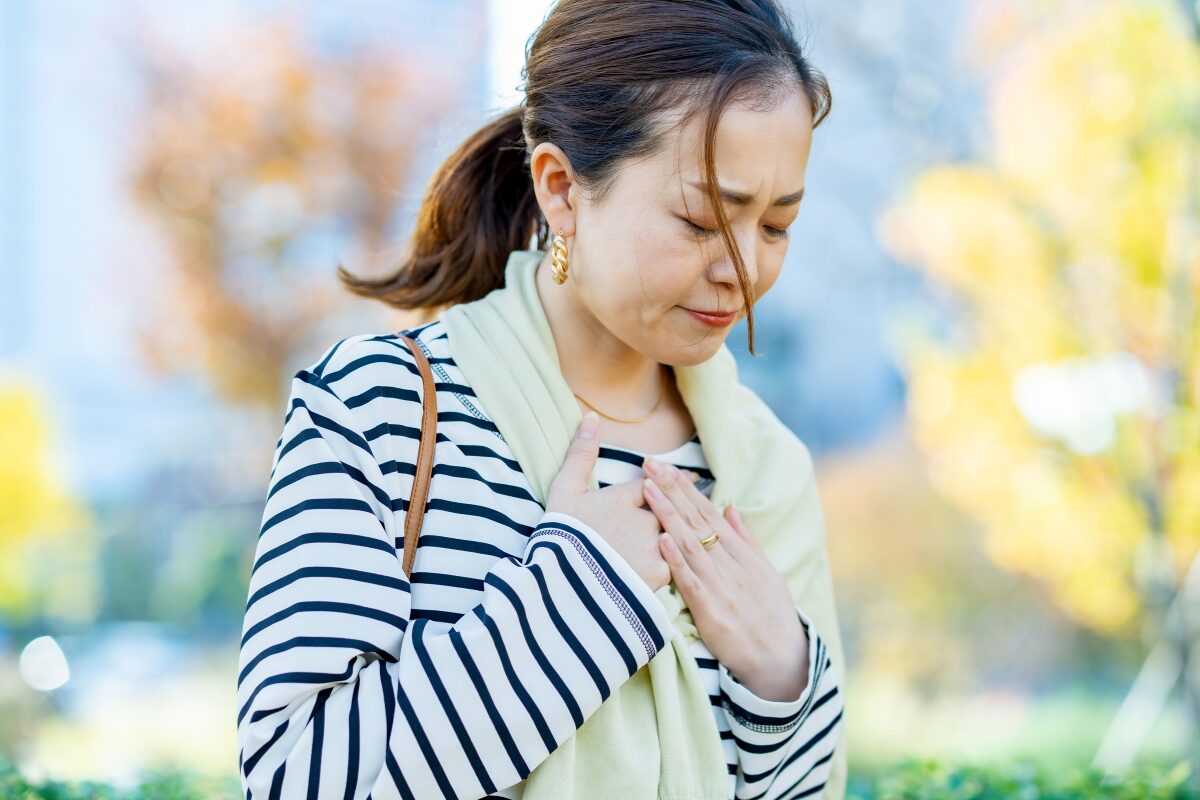
「急に動悸がして息が苦しくなる」その正体は?
パニック発作を経験した方の多くは、
「突然、胸がドキドキして息ができなくなった」
「今にも倒れそうで怖くなった」
と語られます。
ところが、こうした症状を一つずつ見ていくと、実は低血糖発作の症状と非常によく似ています。
たとえば――
-
胸のドキドキ(動悸)
-
息苦しさ、過呼吸
-
手足の震え
-
冷や汗
-
めまい、ふらつき
-
強い不安感や恐怖感
これらは、どちらの発作でも共通して現れるものです。
血糖値が急に下がると、体は「エネルギーが足りない、命の危険だ」と判断し、アドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンを分泌します。
このホルモンが心拍数を上げ、体を緊張させ、脳に「危険!」という信号を送るのです。
その反応がまさに、パニック発作とそっくりな状態になります。
「心の問題」ではなく「体の反応」の場合も
パニック障害は、長らく「心の病」として扱われてきました。
もちろん、心のストレスやトラウマが関係している場合もありますが、
実際には体のエネルギー代謝の乱れが引き金になっているケースも多いのです。
血糖値が乱高下すると、脳が安定したエネルギーを得られず、
その結果として不安や焦燥感が生まれます。
このとき感じる不安は、心理的なものではなく、生理的な防御反応とも言えます。
整体の現場でも、「甘いものを控えたら発作が減った」「間食を工夫しただけで気分が安定した」と話される方が少なくありません。
つまり、心の落ち着きは、**体の安定(特に血糖の安定)**と密接に関係しているのです。
パニック障害と低血糖を見分けるヒント
次のような特徴がある場合は、低血糖の影響を受けている可能性が高いです。
-
空腹時や食後しばらくしてから発作が起こる
-
甘いものやパンを食べたあとに眠くなる、イライラする
-
食事を抜くと手足が震えたり、不安感が強くなる
-
甘いものを食べると一時的に落ち着く
こうしたサインがある場合、「心の不調」と思っていた症状が、実は血糖値の乱れからくる体の反応かもしれません。
そして、この血糖値の変動を引き起こしているのが、「反応性低血糖症」と呼ばれる状態です。
次では、この反応性低血糖症について、もう少し詳しく見ていきましょう。
反応性低血糖症とは?

食後に起こる「血糖のジェットコースター」
反応性低血糖症とは、食後に一度上がった血糖値が、急激に下がってしまう状態を指します。
通常、食事をすると血糖値が上がり、すい臓からインスリンというホルモンが分泌されて、血糖を一定に保とうとします。
しかし、甘いものや白米・パンなどの精製された糖質を多く摂ると、血糖値が急上昇し、それに反応してインスリンが過剰に分泌されます。
その結果、血糖値は必要以上に下がり、今度は体が「エネルギー不足」と判断してアドレナリンやコルチゾールを放出します。
これにより、心拍数が上がり、手が震え、冷や汗が出る――
まさにパニック発作と同じ反応が起こるのです。
このように、血糖の急上昇と急降下を繰り返す状態は、まるでジェットコースターのような血糖の波。
体も心も落ち着かず、常に不安定な状態に置かれてしまいます。
なぜ反応性低血糖が起こるのか?
原因として多いのは、次のような生活習慣です。
-
甘いお菓子や飲み物をよく摂る
-
パンやパスタなど、炭水化物中心の食事が多い
-
朝食を抜く、または食事の間隔が長い
-
カフェインの摂りすぎ(血糖値を乱す)
-
睡眠不足やストレスで副腎が疲れている
特にストレスが強いと、血糖を安定させるためのホルモンが過剰に分泌され、
結果的に血糖コントロールがうまくいかなくなります。
つまり、ストレスと食生活が組み合わさることで、反応性低血糖が悪化するのです。
「血糖の乱れ」は心にも影響する
血糖が乱れると、脳が安定したエネルギーを得られず、
集中力の低下、イライラ、無気力、不安感といったメンタル面の不調が現れやすくなります。
とくに、脳はブドウ糖を唯一のエネルギー源としているため、
血糖値の乱高下がそのまま心の不安定さにつながってしまうのです。
この状態が長く続くと、脳や自律神経が常に緊張モードになり、
「いつ発作が起きるか分からない」という不安が習慣化していきます。
その結果、体の反応が本格的なパニック障害へと発展してしまうこともあります。
整体から見た反応性低血糖の特徴
整体の視点で見ると、反応性低血糖の人は次のような特徴を持つことが多いです。
-
常に肩や首が緊張している
-
胃腸の働きが弱く、食後にだるくなる
-
冷えやすく、手足の血流が悪い
-
息が浅く、呼吸が速い
-
自律神経の切り替えがうまくいかない
これらはすべて、血糖の乱れと関係しています。
体の緊張をゆるめ、自律神経を整えてあげることで、
血糖コントロールも自然と落ち着いていくのです。
次の章では、こうした状態を改善するために役立つ栄養療法のポイントを詳しくご紹介します。
パニック障害への栄養療法

血糖値を安定させる食事を意識する
パニック障害の背景にある反応性低血糖を改善するには、まず血糖値を安定させることが大切です。
血糖値の乱高下を防ぐには、急激に血糖を上げる食べ方を避けることがポイントになります。
食事では、最初にごはんやパンなどの糖質を食べるのではなく、たんぱく質や野菜を先に食べる「ベジ・ファースト」を意識しましょう。
また、糖質の摂りすぎを防ぐために、食事のたびに肉・魚・卵・豆類などをしっかり摂ることも重要です。
これにより血糖値の上昇がゆるやかになり、心の安定につながります。
精製糖質を減らす
白砂糖、白米、パン、パスタなどの精製された糖質は、血糖値を急上昇させやすい食品です。
このような食べ物を頻繁に摂ると、インスリンの過剰分泌を招き、結果的に低血糖状態を引き起こします。
甘いお菓子や清涼飲料水、カフェオレなども要注意です。
「ちょっと疲れたから」と甘いものを摂ると、一時的に元気になったように感じますが、
そのあとに強いだるさや不安感が出る人は、血糖の乱れを起こしている可能性があります。
完全にやめるのが難しい場合は、まず「間食を減らす」「甘味料を自然なもの(はちみつや果物)に変える」など、
無理のない範囲で工夫してみましょう。
補食を上手に取り入れる
低血糖が起こりやすい人は、食事の間隔を空けすぎないことが大切です。
1日3食に加えて、軽い補食(おやつ)を1〜2回取り入れると安定しやすくなります。
おすすめは、
-
ナッツ類(くるみ、アーモンドなど)
-
ゆで卵
-
チーズ
-
無糖ヨーグルト
-
プロテインドリンク
といった、血糖を急激に上げないもの。
おにぎりや菓子パンよりも、たんぱく質と脂質を含む補食のほうが長時間エネルギーが持続します。
胃腸を整える
どれだけ良い栄養を摂っても、胃腸の働きが弱っていると吸収されません。
低血糖を繰り返す人は、胃腸が冷えていたり、緊張で消化力が落ちていることも多く見られます。
整体では、呼吸を深めたり、みぞおちや腹部の緊張をゆるめることで、胃腸の働きを整えることができます。
胃腸が整うと、食べ物の消化・吸収が良くなり、血糖コントロールも自然と安定していきます。
タンパク質をしっかり摂る
心と体の安定のために、たんぱく質は欠かせません。
たんぱく質は血糖の安定を助けるだけでなく、脳内で「安心感」をつくるセロトニンやGABAなどの神経伝達物質の材料になります。
肉・魚・卵・豆類などを、毎食の中心に据える意識を持ちましょう。
朝食に卵や納豆、昼食に魚、夕食に肉など、1日の中でバランスよく取り入れると、
エネルギーも気分も安定しやすくなります。
栄養療法は「心を支える食べ方」
栄養療法というと難しく感じるかもしれませんが、基本は「血糖を乱さない食べ方」を続けることです。
その積み重ねが、神経を穏やかにし、発作を起こしにくい体づくりにつながります。
そして、食事と並行して整体で自律神経のバランスを整えることで、
体の緊張がゆるみ、ホルモンや血流、代謝もスムーズに働くようになります。
【関連ページ】

