
なんだか最近、疲れやすい。
食後しばらくするとイライラしたり、急に不安になったりする。
そんな症状が続いているけれど、病院では「異常なし」と言われてしまった……。
それはもしかすると、「機能性低血糖症」かもしれません。
機能性低血糖症とは、血糖値が正常範囲内であっても、急激に下がることで心身にさまざまな不調を引き起こす状態です。
症状は、疲労感・集中力の低下・気分の波・動悸・眠気など多岐にわたり、放っておくと日常生活に支障をきたすこともあります。
そしてこの機能性低血糖症は、自律神経の働きと深い関係があります。
実は整体によって自律神経を整えることで、こうした血糖の乱れによる不調が改善されるケースも多く見られます。
この記事では、機能性低血糖症とは何か、そして整体でどのようにアプローチできるのかを、わかりやすく解説していきます。
「原因がわからない不調」にお悩みの方にとって、回復のヒントになれば幸いです。
機能性低血糖症とは?

■ 血糖値は正常でも不調が出る?
「低血糖」と聞くと、糖尿病の治療をしている人がインスリンを打ちすぎたときなどに起きるもの、というイメージがあるかもしれません。
しかし実は、糖尿病でなくても血糖が乱れることで不調が出ることがあります。それが「機能性低血糖症」です。
機能性低血糖症は、血糖値が正常範囲内にあっても、急激に下がることによって身体や精神にさまざまな不調が現れる状態です。
これは特に、食後2〜3時間ほど経ったころに起きやすく、以下のような症状が典型的です:
-
強烈な空腹感(食べたばかりなのにまた食べたくなる)
-
イライラ、怒りっぽさ、落ち着かない感じ
-
頭がボーっとする、集中できない
-
急な眠気、強い疲労感
-
動悸や冷や汗
-
不安感や焦燥感、パニックに近い精神症状
-
抑うつ状態、やる気の低下
本人や周囲からは「性格の問題」「ストレスに弱い」「わがまま」と誤解されやすく、見過ごされがちです。
しかし、体内では確実に血糖コントロールの乱れが起きており、放置することでさらに心身のバランスを崩してしまうこともあります。
■ なぜ血糖が乱れるのか?
血糖値は、私たちの体がエネルギーを安定的に供給するうえで重要な指標です。
通常、食事をすると血糖値が上がり、それに反応して膵臓からインスリンが分泌され、血糖値を一定に保とうとします。
ところが、次のような条件が揃うと、インスリンが過剰に分泌されたり、逆に血糖を上げるホルモンの働きが鈍くなったりして、急激な血糖値の下降(=低血糖状態)が起きやすくなります。
主な原因は以下の通りです:
-
糖質に偏った食生活(白米、パン、甘いお菓子や清涼飲料水などの摂りすぎ)
-
たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラル不足(血糖を安定させる栄養が足りない)
-
朝食抜きや長時間の空腹状態(血糖の変動が大きくなる)
-
過剰なストレスや慢性的な緊張状態(自律神経の乱れ)
-
睡眠不足・過労(ホルモン調整がうまくいかなくなる)
これらの要因が組み合わさることで、血糖のバランスが崩れ、体が必要以上にインスリンを分泌したり、逆に血糖を持ち上げるホルモンが追いつかなくなったりします。
その結果、血糖が「ジェットコースター」のように乱高下するようになり、心身の不調を引き起こします。
■ 一般の検査では「異常なし」とされやすい
機能性低血糖症がやっかいなのは、通常の健康診断ではまず見つからないという点です。
血液検査では食後のタイミングや血糖の変化の推移を調べることがないため、「正常範囲」とされ、見逃されてしまいます。
症状だけを見ると、自律神経失調症、うつ病、不安障害、更年期障害などと診断されることもあり、
根本的な対処がされないまま、長く苦しむ方も少なくありません。
しかし、実際には栄養状態と血糖バランスの見直し、自律神経を整えることによって、
症状が劇的に改善するケースも多く存在します。
自律神経と血糖コントロールの深い関係
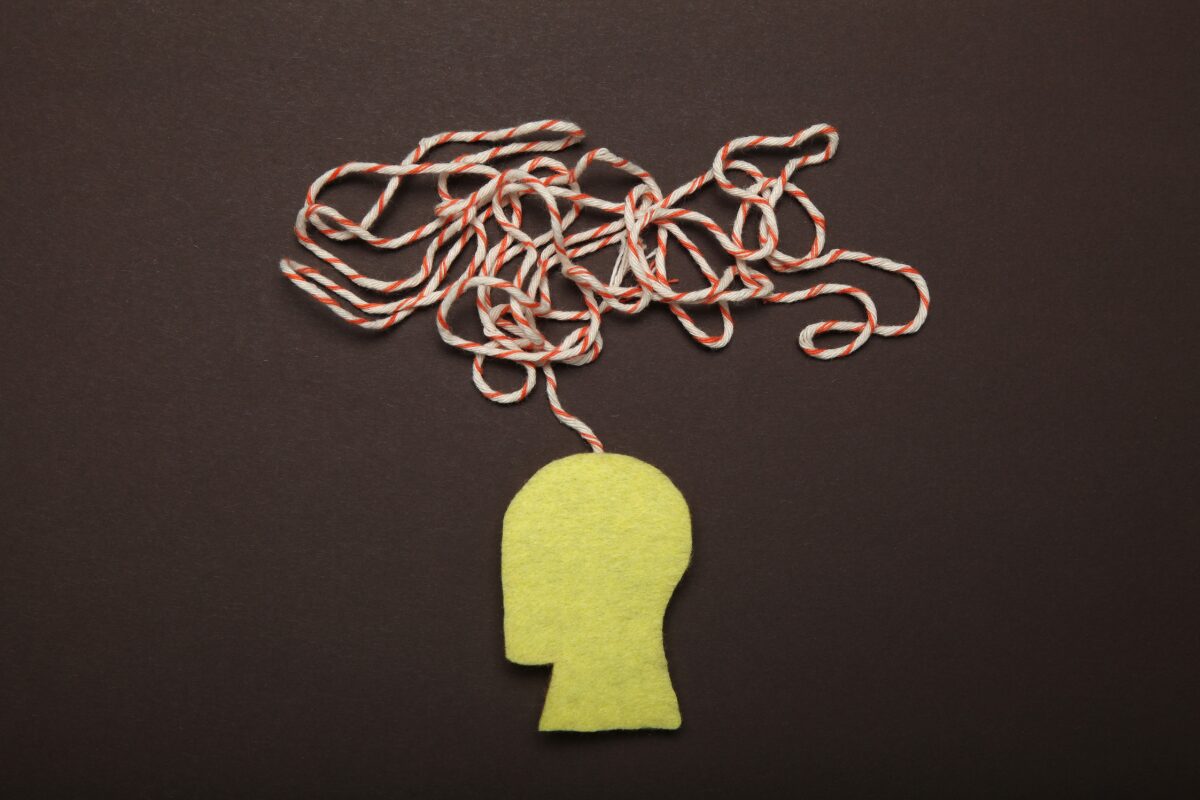
~機能性低血糖症と整体の視点から~
■ 自律神経は血糖を裏で支えるコントロールセンター
機能性低血糖症の背景には、自律神経の乱れが密接に関わっています。
私たちの体は、食後の血糖値を安定させるためにインスリンなどのホルモンを分泌していますが、
それだけでなく、自律神経もまた血糖のコントロールに大きな役割を担っています。
自律神経には、交感神経と副交感神経があり、体の活動と休息をバランス良く切り替えています。
しかし、日常的にストレスが多かったり、睡眠不足や緊張状態が続いていたりすると、
このバランスが崩れ、血糖値を正常に保つための仕組みがうまく働かなくなります。
とくに機能性低血糖症の方は、副交感神経がうまく働かず、血糖の急降下に対して過剰に反応してしまうことがあります。
これにより、動悸・焦燥感・不安などが出るケースも見られます。
■ ストレスと血糖の乱れ、その悪循環
ストレス社会の現代では、交感神経が常に優位になりがちです。
これは、「戦うか逃げるか」の緊張モードが続いている状態であり、体は常にエネルギーを使う準備をしています。
このとき、血糖を上げるホルモン(アドレナリンやコルチゾールなど)が頻繁に分泌され、
一時的に血糖は上がりますが、その反動で急激に下がることも少なくありません。
その結果として、甘いものを欲したり、イライラしたり、集中できなかったりといった、
機能性低血糖症に見られる典型的な症状が現れるのです。
こうした血糖の乱高下は、自律神経にもさらなる負担をかけるため、症状が長期化・慢性化しやすくなります。
■ 血糖の乱れが自律神経を乱し、さらに低血糖を招く
一度、血糖コントロールのリズムが崩れてしまうと、
今度は自律神経自体が影響を受けやすくなり、交感神経が過剰に働く状態が常態化します。
このような状態では、食事をしてもすぐに血糖が落ちてしまい、体が不安やだるさを感じやすくなります。
とくに機能性低血糖症の方は、ほんの少しの血糖の落ち込みでも過敏に反応するため、
「いつも気が張っている」「眠りが浅い」「朝がつらい」などの不調を訴えることが多く見られます。
■ 整体で整う、自律神経と血糖のバランス
こうした悪循環を断ち切るために有効なのが、整体による自律神経へのアプローチです。
整体では、骨格や筋肉のバランスを整えるだけでなく、
緊張状態が続いている神経系に対しても、リラックスを促す働きかけができます。
特に背骨や骨盤の歪みは、自律神経の中枢である脊髄の働きに影響するため、
ここを整えることで、副交感神経がしっかりと働きやすい状態をつくることができます。
その結果、ホルモンのバランスも整い、血糖の安定にもつながっていきます。
また、整体の施術中に深い呼吸が自然と生まれることも、機能性低血糖症の改善に有効です。
呼吸が深まると副交感神経が優位になり、血糖を乱れにくくする体質へと導いてくれます。
機能性低血糖症の改善セルフケア

機能性低血糖症を改善するためには、血糖値の急激な変動を防ぎ、安定した状態を保つことが重要です。
そのためには、食生活の改善と生活習慣の見直しが不可欠です。
以下に、機能性低血糖症を改善するための具体的な方法を紹介します。
1. 精製糖質の摂取を減らす
精製糖質(白砂糖、白米、白パンなど)は血糖値を急激に上昇させ、その後急速に下がることを引き起こします。
この急激な変動が低血糖症の原因となり、さらに自律神経の乱れを招きます。
精製糖質の摂取を減らし、以下のような食材に置き換えることが効果的です。
-
全粒穀物(玄米、全粒粉パン、オートミールなど)
全粒穀物は、精製されていないため消化に時間がかかり、血糖値が緩やかに上昇します。 -
野菜や果物
食物繊維が豊富な野菜や果物は血糖値の急上昇を防ぐだけでなく、満腹感を長時間保つのに役立ちます。 -
良質な脂肪とタンパク質
ナッツ、アボカド、オリーブオイル、魚(サーモン、サバなど)などの良質な脂肪や、鶏肉、卵、大豆製品などのタンパク質を摂取することも血糖値の安定に寄与します。
2. 食事の回数とタイミングに注意
食事の回数やタイミングを工夫することも、血糖値を安定させるためには重要です。
-
1日3食+軽食
食事を1日3回ではなく、3回の食事に加えて軽食(間食)を摂ることで、血糖値の急激な変動を防ぎます。
軽食は、ナッツやチーズ、ヨーグルトなど、血糖値を急激に上げない食品を選びましょう。 -
朝食を必ず摂る
朝食を抜くと、血糖値が低い状態で日中を過ごすことになり、低血糖症の症状が出やすくなります。
朝食には、タンパク質や食物繊維を含んだ食品を選ぶと良いでしょう。
3. ストレス管理とリラックス
ストレスは血糖値の乱れを引き起こし、自律神経の不調を悪化させます。
ストレスを減らし、リラックスした状態を作ることが重要です。
-
深呼吸や瞑想
簡単な深呼吸や瞑想を日常生活に取り入れることで、交感神経の過剰な働きを抑え、副交感神経を活性化させることができます。 -
軽い運動
毎日の軽い運動(ウォーキングやヨガ、ストレッチなど)は、血糖値を安定させ、ストレスを減らすのに効果的です。
4. 規則正しい生活リズム
生活リズムが乱れると、ホルモンバランスや自律神経に悪影響を与えます。
規則正しい生活を送ることが、血糖値の安定を助け、機能性低血糖症の改善に繋がります。
-
十分な睡眠
良質な睡眠を確保することで、体の回復力が高まり、血糖値を安定させるホルモンの分泌が促されます。睡眠は1日7~9時間を目安に、毎日同じ時間に寝るよう心がけましょう。 -
食事と睡眠のタイミング
食後すぐに横にならないようにし、夕食は寝る2~3時間前に摂るようにすると、血糖値の乱れを防げます。
【関連ページ】


